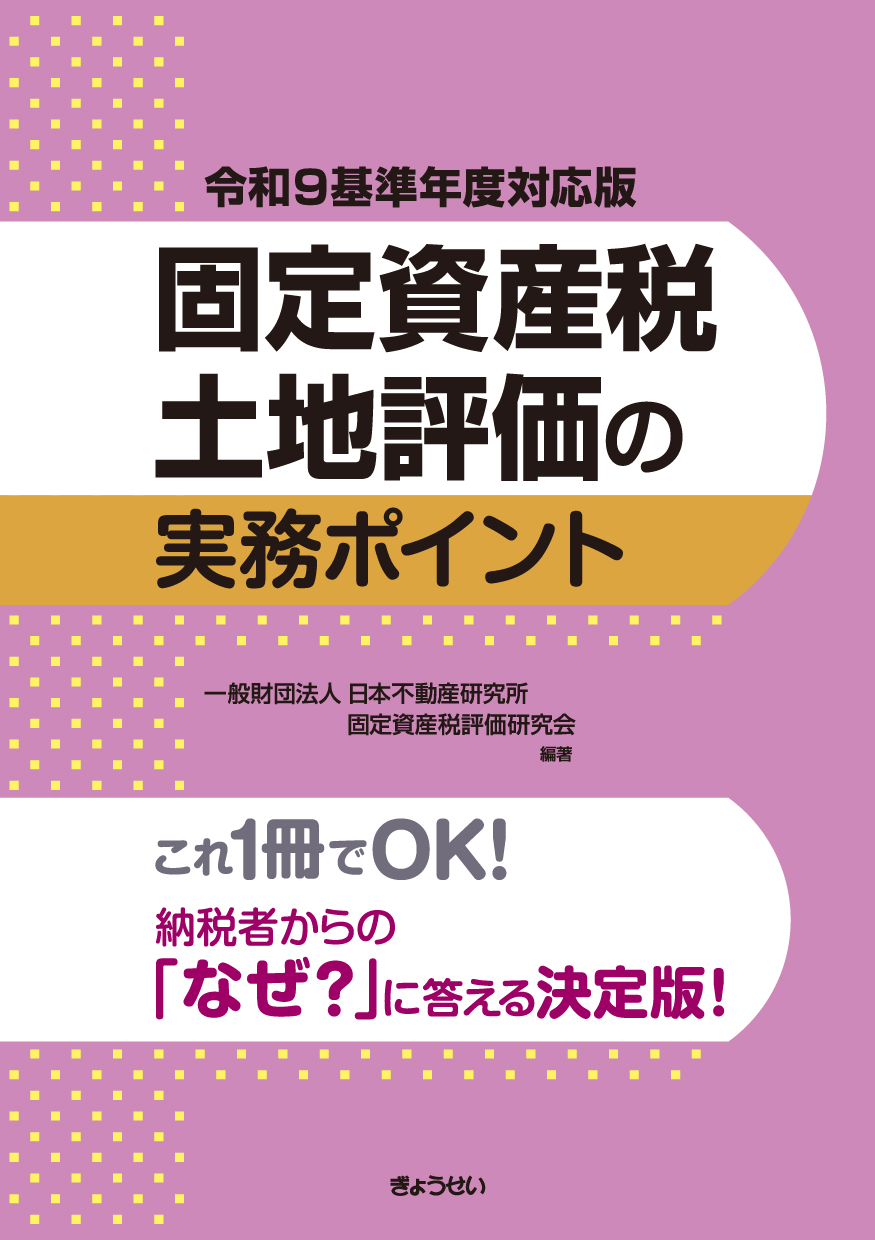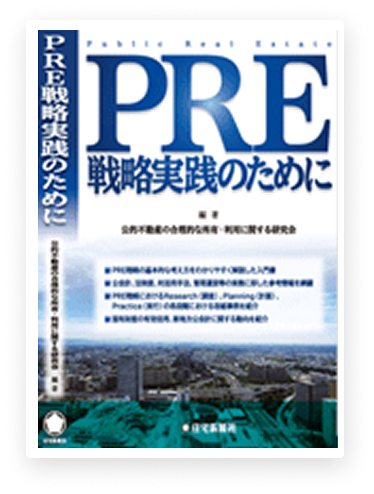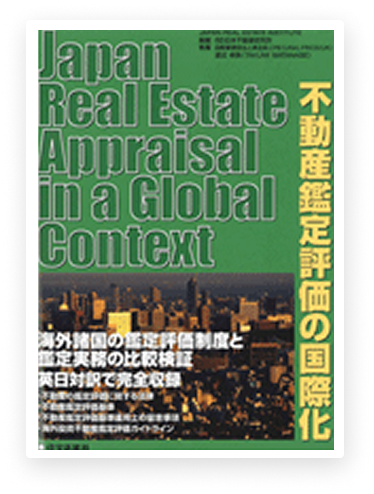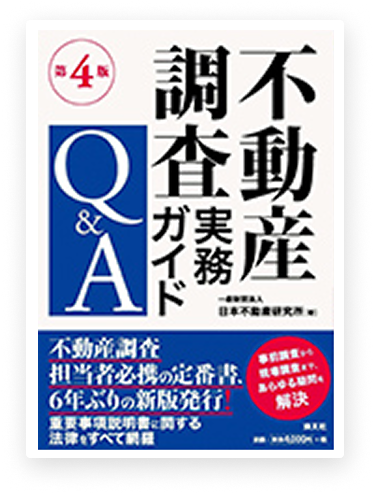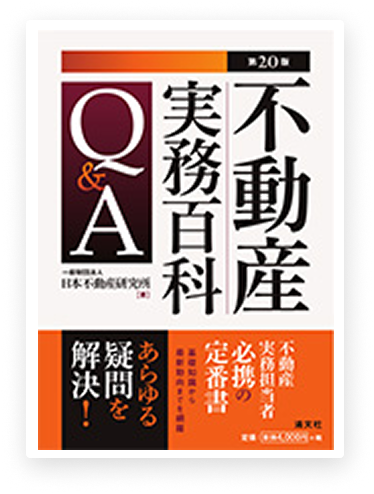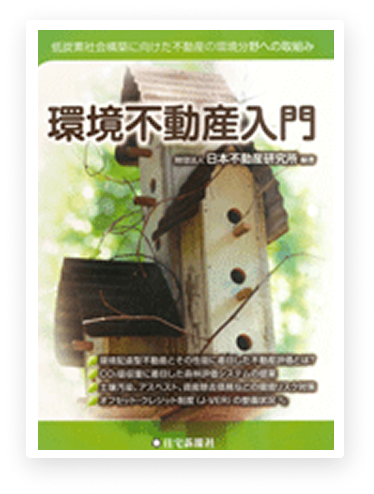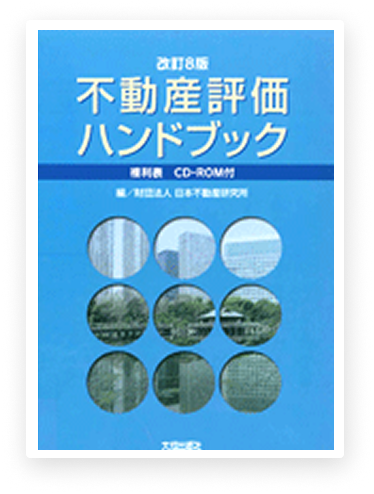コンサルティングなどの事業を通して培った情報やノウハウを定期刊行物、専門書籍として多数出版しております。
どの出版物も、実際に不動産業界に携わる方々の業務に活かしていただけるよう、実用性を重視して制作されています。どうぞみなさまのお仕事にお役立て下さい。
※ 書籍の購入等については、各販売元(出版社)にお問い合わせ願います。
令和9基準年度対応版 固定資産税土地評価の実務ポイント
日本不動産研究所固定資産税評価研究会[編著](株式会社ぎょうせい 3,630円+税)
特別価格3,300円+税
Q&A固定資産税家屋評価の実務ポイント
日本不動産研究所固定資産税評価研究会[編著](株式会社ぎょうせい 3,630円+税)
特別価格3,300円+税
不動産調査実務ガイドQ&A 第4版
日本不動産研究所 著(清文社・4,200円+税 A5判)
不動産実務百科Q&A 第20版
日本不動産研究所 著(清文社・4,000円+税 A5判)
不動産研究第60巻記念号
「土地バブル、バブル崩壊、そして証券化へ」
日本不動産研究所 編(日本不動産研究所・3,000円+税)
ベーシック不動産入門<第4版>
日本不動産研究所 編(日本経済新聞出版社・1,000円+税)
PRE戦略実践のために
(「PRE戦略を実践するための手引書(改訂版)」編集)
公的不動産の合理的な所有・利用に関する研究会(PRE研究会) 編著(住宅新報社・2,800円+税 A5判)
環境不動産入門
日本不動産研究所編著(住宅新報社・2,000円+税)
資産除去債務の実務-対象債務の抽出と会計処理
日本不動産研究所/新日本有限責任監査法人 編(中央経済社・3,000円+税)
不動産用語辞典<第7版>
日本不動産研究所 編(日本経済新聞出版社・900円+税)
Japan Real Estate Appraisal in a Global Context
(不動産鑑定評価の国際化)
日本不動産研究所 編著(住宅新報社・3,400円+税)
不動産評価ハンドブック<改訂8版>
日本不動産研究所 編(大成出版社・6,000円+税)
内容
月刊「税」・「ここが知りたい
最新税務Q&A」の家屋評価の集大成。家屋評価において、市町村職員が実務上直面する課題をピンポイントで解説した実務書です。
本書の特色
・読者の疑問にピンポイントで回答できるようにQ&A形式で解説。
・「トレーラーハウスを家屋と認定する要件」「特殊な家屋の評価」「複合構造・複合用途家屋の評価」など、実務で直面する課題をピックアップしています。
目次
- 刊行にあたって
- はしがき
- 第1篇 固定資産税の土地評価~総論~
- 第1章 地目別の評価方法
- 第2章 宅地の評価方法
- 第3章 宅地の評価における所要の補正
- 第2篇 標準宅地の鑑定評価
- 第1章 固定資産税評価における不動産鑑定評価の活用の意義
- 第2章 標準宅地の鑑定評価書の見方
- 第3章 主要な街路の路線価の付設
- 第3篇 固定資産税の土地評価~各論~
- 第1章 市街化区域農地の評価
- 第2章 画地認定についての考察
- 第3章 土地区画整理事業施行地区にある土地の評価
- 第4章 不整形地の評価(不整形地補正)
- 第5章 災害ハザードエリアにある土地の評価
- 第6章 その他の雑種地の評価
- 参考資料
内容
月刊「税」・「ここが知りたい
最新税務Q&A」の家屋評価の集大成!
「令和6基準年度対応版 固定資産税土地評価の実務ポイント」に続き、家屋評価においても、内容をわかりやすく、かつ、市町村職員が実務上直面する課題をピンポイントで解説したものです。
本書の特色
・読者の疑問にピンポイントで回答できるようにQ&A形式で解説!
・「トレーラーハウスを家屋と認定する要件」「特殊な家屋の評価」「複合構造・複合用途家屋の評価」など、
固定資産税家屋評価の実務で直面する課題をピックアップ!
目次
- 刊行にあたって
- はしがき
- 第1篇 家屋の認定
- 第2篇 家屋の床面積
- 第3篇 新築家屋の評価
- 第1章 再建築費評点基準表の適用
- 第2章 各種仕上の評価
- 第3章 建築設備及び建具等の評価
- 第4章 仮設工事及びその他工事
- 第5章 特殊な家屋の評価
- 第6章 複合構造・複合用途家屋の評価
- 第7章 比準による再建築費評点数の算出方法
- 第8章 区分所有家屋の評価・課税
- 第4篇 既存家屋の評価
- 第1章 改築が行われた家屋の評価
- 第2章 再建築費評点補正率について
- 第5篇 他の固定資産(土地・償却資産)との関連
- 参考資料
内容
不動産は、書類だけではわからないことが数多く存在します。不動産の価格は、その不動産が置かれた状態をしっかりと把握しなければ、導き出すことはできません。不動産調査の重要性は、このような「現地調査を通じて価値を顕在化させる」ことにあります。そして現地調査によって価値を見出すためには、事前にその不動産の登記・法規制・権利関係等に関する調査を行い、多くの経験をもとに判断することが必要です。
本書は、不動産取引のために不動産を調査するにあたり、関係があると思われる知識を簡潔にわかりやすく説明するよう心がけました。特に、不動産は資料に記録されている内容と、現実の状態が異なることも多々ありますので、記録と現実の状態に違いが生じた場合の解消方法について、不動産鑑定士の実務経験をふまえて説明しています。
本書を用いて不動産調査の経験を重ねることで、不動産の価値を見極めるための「直観力・目利き力」を養うことに繋がれば幸いです。
目次
- 第1章 不動産調査の基本的事項
- 第2章 登記資料の調査
- 第3章 権利関係の調査
- 第4章 現地調査
- 第5章 法令上の制限に関する調査
内容
3年に1度の土地評価替えに向けた最新版。前版を改良し、時節に応じた内容を補強した改訂版です。
本書の特色
・イラストを交えわかりやすく実務ポイントや留意点を解説。
・市街化区域農地の評価や画地認定についての考察など新規テーマを収録。
目次(抜粋)
- 刊行にあたって
- はしがき
- 第1篇 固定資産税の土地評価~総論~
- 第2篇 標準宅地の鑑定評価
- 第3篇 固定資産税の土地評価~各論~
不動産は人間が生活し活動するために欠くことができない基盤です。そして、それは限られた貴重な財産であることを、不動産ビジネスに携わる人は、しっかり意識し、必要な知識を身につけて活動しなければなりません。
本書は、複雑かつ多岐にわたる不動産にかかわる制度や法律について、不動産の実務(取引や管理、投資など)を行う際の手順に沿って章立てし、すぐにわからないことを解決できるよう、Q&Aの方式で解説します。また、各種手続きに必要な申請書についてもサンプルを掲載し、イメージしやすいように構成しました。
本書は、不動産実務に初めて携わる人、マイホームの購入を検討している人、不動産投資を始めたいと考えている人など、どなたでもわかるような内容としています。読者の皆様が不動産の知識を広く、まんべんなく理解いただき、実務や不動産取引にあたって有効に活用していただければ幸いです
日本不動産研究所の発行する「不動産研究」は、発足から間もない1959(昭和34)年7月に第1巻第1号(創刊号)が発刊されましたが、お陰様をもちまして、本年には第60巻という節目を迎えることができました。その間、皆様に本誌をお支えいただきましたことに、改めて深く御礼を申し上げます。
さて、第60巻記念号につきましては、「土地バブル、バブル崩壊、そして証券化へ」をテーマに、昭和の終わりから平成の初めのバブル期の地価高騰とその後の不動産を巡る動きについて、関係者がどのように状況を認識し、どのような考え方の下に対策を講じていったのか、ということを中心に、特集を組みました。
本号が、お読みいただく皆様にとりまして、過去を振り返り、新たな時代を考えるよすがとなり、不動産市場のさらなる発展へとつながれば、望外の喜びです。
「数え」で60回目の設立の日にあたり、弊所役職員一同、誓いを新たに精一杯努力する所存でございますので、引き続きのご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
主な内容
土地行政・銀行行政等の関係者からのインタビューを集めた政策編、リート、住宅ローンの証券化の立ち上げのインタビューを集めた不動産金融の新展開編、バブルを目の前で見た不動産鑑定評価の専門家のインタビューを収録した不動産鑑定編の3部から構成。
このほか、市街地価格指数による地価動向、不動産研究掲載論文、年表等をあわせて収録。
主な情報
発行 : 2018年2月24日(土) / 定価 : 3,000円+税 / 頁数 : 336(予定) / 判型 : A4版
不動産、特に土地に対する見方や考え方が、バブル崩壊後、長期間の地価の下落を経て、土地そのものの資産価値は実は不安定であり、目減りする資産であることが改めて明らかになりました。不動産に対する考え方が「所有から利用へ」と大きく変化し、さらには、環境への配慮も必要となり、不動産価値の多様化が進んでいます。住宅の売買や賃貸など不動産にかかわる問題は、日常の生活でどこでも起こり、企業においては、不動産の証券化、土壌汚染リスク、CRE戦略などの言葉を耳にすることが多くなっています。本書は、それらに対処するために、あらかじめ契約や取引、登記や税金、評価や金融、さらには環境など、幅広い知識を習得できるように、不動産に関する各方面の基礎的な知識を網羅し、できるだけ専門用語は使わずに解説しています。
第4版は、約9年ぶりの大幅な改訂であり、不動産を取り巻く状況の変化に応じて見直しを行い、特に、Ⅶ章の「不動産証券化と不動産投資市場」は全面的な見直しを行い、Ⅷ章の「環境と不動産」は新設を行いました。
PRE(Public Real
Estate)戦略とは、公的不動産について、公共・公益的な目的を踏まえつつ、経済の活性化及び財政健全化を念頭に、適切で効率的な管理、運用を推進していこうとする考え方です。地方公共団体における資産・債務改革の更なる推進に向けて、新地方公会計制度に基づく財務書類の作成、資産台帳の整備が進みつつあるなかで、これら資産情報をPRE戦略におけるResearch(調査)と位置づけて、各地方公共団体の状況に応じたPRE戦略構築への取組みも見られるようになってきています。
本書は、国土交通省が平成22年5月に公表した「PRE戦略を実践するための手引書(改訂版)」を基本に、総務省、財務省より最新情報のご提供を頂き、総務省、国土交通省、PRE研究会、日本不動産研究所で出版事務局を組織して編集したものです。
低炭素社会構築に向けた温室効果ガス削減諸制度の創設・改正や、企業のCSR活動の活発化などにより、建物の省エネルギー・省資源や、CO2吸収機能に注目した森林整備などへの関心が高まっています。
また、土壌汚染対策法の改正に伴い、土壌汚染対策などについても新たな展開が予想されます。
しかし、この分野は情報の不足度が高く、市場の認識も高くはないのが現実です。
本書は、以下の内容で不動産の環境分野に関する最新情報と基礎知識を平易に解説し、情報収集の方法や評価の考え方なども紹介することにより、不動産の環境意識の向上を図ることをねらいとしています。
資産除去債務に関する会計基準・適用指針が平成22年4月1日以後開始する事業年度から適用されています。資産除去債務の会計処理については、見積りの要素が強いことや環境法令等の知識が必要となること等により、実務上判断に迷うケースが多く生じています。
本書は、資産除去債務の具体的な会計処理・開示、資産除去債務の対象となる環境対策義務・原状回復義務の法規制、さらに会計基準を適用する際に生じる疑問点・留意事項等について、設例を用いて詳細に解説しています。また、論点ごとにポイントを整理しています。
昭和51年の初版刊行以来、不動産関係の基本的な用語を幅広く網羅し、その折々の重要な用語を取り入れながら改訂を行ってきた用語辞典の第7版。Jリート、不動産投資インデックス、アセットマネジメント、オリジネーターなど、不動産証券化時代に対応した用語はもちろん、近年話題となっている土壌汚染、アスベスト、耐震構造、減損会計など最新のキーワードまで網羅し、さらに、独特の法律用語、難解なカタカナ用語も平易に解説しています。
国際評価グループが2002年に企画・実施した『英語で読む不動産鑑定評価基準』をベースに、その後の数多くの国際評価業務の実務経験、証券化と鑑定評価に係る海外調査の成果、国内外の評価基準の大改正、関連国際会議での議論、国交省海外評価ガイドライン委員会での議論等を踏まえ、日本の鑑定評価を、国際的文脈の中で解説(英日対訳で構成)しています。
目次
- 第1編 日本の不動産鑑定評価の展開と特質
- 第2編 不動産の鑑定評価に関する法律
- 第3編 不動産鑑定評価基準
- 第4編 不動産鑑定評価基準運用上の留意事項
- 第5編 海外投資不動産鑑定評価ガイドライン
不動産をめぐる社会・経済情勢の変化に対応すべく、改訂と増補、さらにはコンパクト化も考慮して第8版を刊行しました。主な改訂・増補点は以下のとおりです。
構成(抜粋)
- 第1部の評価資料編では、第1章は、財産評価基本通達及び固定資産評価基準につき各々の改正を織り込み、評価の方法及び特別な事情のある宅地や権利等の評価要領と、税額の計算方法を紹介しています。第3章の「環境基準」は、「アスベスト」に加えて土壌汚染を加筆修正してあります。
第4章は法規制の内容をコンパクトに「注意すべき不動産規制」とし、第5章の「関連統計資料」は、最新の情報に更新しました。
- 第2部の数値表編では、EXCELでの計算ファイルをCD-ROMとして付け、従来よりも使い勝手を改良しました。