【土地と人間】AI価格査定はどこに向かう?
みなさんこんにちは、日本不動産研究所の幸田 仁です。 生成AIは現在、ものすごい速さで技術的な進化が進んでいます。 報道によれば、生成AIに2025年度の大学共通テストを受験させたところ、15科目のう...

不動産に関する分析や季刊誌「不動産研究」への寄稿記事、
不動産トピック、流行、潮流などのコラム、
その他各種データや指標等の不動産レポートなどを掲載しています。
みなさんこんにちは、日本不動産研究所の幸田 仁です。 生成AIは現在、ものすごい速さで技術的な進化が進んでいます。 報道によれば、生成AIに2025年度の大学共通テストを受験させたところ、15科目のう...
住宅新報2026年2月10日号 特集『不動産流通市場の回顧と展望』掲載記事より 不動産流通市場の回顧と展望~2025年までの10年間における中古住宅流通市場の変遷を中心に~ 研究部 主席専門役 曹 雲...
みなさんこんにちは、日本不動産研究所の幸田 仁です。 令和8年(2026年)は、午(うま)年ですが、十干十二支で数えると「丙午(ひのえうま)」の年になります。この丙午の年は、60年に一度巡ってくる特別...

世界第2位の二酸化炭素排出国であるアメリカの連邦政府は、2025年1月にパリ協定からの脱退を発表した。COP30へのアメリカの動向はどのようなものだったか
COP30の閉会の挨拶で、シモン・スティール国連気候変動枠組条約事務局長が発した”mutirão”(ムティロン)とはどういう意味か
2023年のCOP28で設立が決まったL&D基金は、COP30 でどのような成果が出たか
COP30では、先進国が途上国に気候対策のための資金援助の目標(NCQG:New Collective Quantified Goal)の具体的なロードマップは決まったか?

【持続性】使用木材は北海道産木材 HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE
写真_北広島市

【持続性】構造材・内装材に木材を利用したロッジ HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE
写真_北広島市

【地域との関わり】40年続く街路イルミネーションイベントの運営資金 SENDAI光のページェント
写真_仙台市

【防災・減災】駅構内の止水板格納庫
写真_JR馬喰町駅
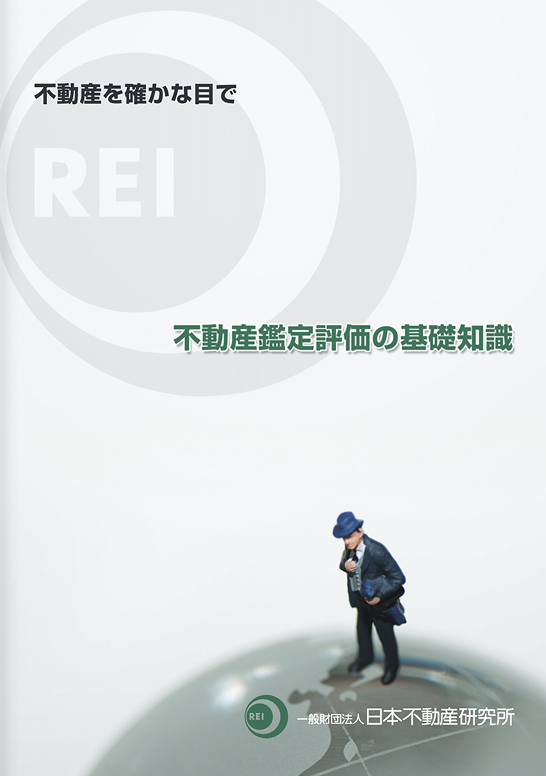 デジタルブック
デジタルブック